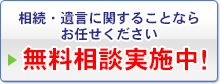松山より相続に関するご相談
2025年05月02日
Q:認知症患者がいる場合の相続手続きはどうしたらいいか司法書士の方に伺います。(松山)
私は松山に住む50代の会社員です。先日、80代の父が松山市内の病院で亡くなりました。松山市にある斎場で葬式を行ったのですが、認知症を患う78になる母が、父が亡くなったことを理解できていない様子だったことがとても悲しく、印象に残っています。
母がそのような状態なので子供である私と弟の2人で亡くなった後の手続きを手分けしてやっています。そろそろ相続手続きも始めなければなりませんので、先日わかる範囲で父の相続財産を調べたところ、松山の自宅と預貯金が1000万円程度でした。あとは戸籍から相続人が母、弟、私の3人であることは確定しています。今後懸念されるのは、認知症の母はどうやって相続手続きに参加したらいいのかということです。たとえ署名や押印はできたとしても、行為の理由や目的は分からないと思います。認知症患者が相続人にいる場合の相続手続きについて教えてください。(松山)
A:相続だけでなく今後の必要性を踏まえたうえで「成年後見人制度」を活用する方法があります。
認知症等により判断能力が不十分とされた相続人は、法律行為である遺産分割をすることができません。だからと言って、「家族だから大丈夫」と相続手続きに必要な署名や押印を認知症の方に代わって他の相続人が行う行為は、たとえ血の繋がったご家族であっても違法となりますのでご注意ください。
相続手続きにおいて、認知症を患う方が相続人の中にいる場合は、「成年後見制度」の利用を検討します。
成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分とみなされた方を保護する制度です。成年後見人という代理人が、認知症の方に代わって遺産分割を成立させます。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に成年後見人の申立てをして、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。成年後見人には以下の者を除き、誰でもなる事が出来ます。また、親族だけでなく、法律の専門家が選任される場合や、複数名が選任される場合もあります。
【成年後見人にはなれない方】
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
なお、成年後見制度を利用させる際に注意していただきたいことがあります。成年後見人は一度選任されると、遺産分割協議が終わった後もその利用が継続します。対象者が亡くなるまで成年後見人に対して報酬を支払い続けることになりますので、目先の相続手続きのためだけではなく、その後も必要かどうかよく考えて検討するようにしましょう。
松山相続遺言相談室では、松山のみならず、松山周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。松山相続遺言相談室では松山の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、松山相続遺言相談室では松山の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
松山の皆様、ならびに松山で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました
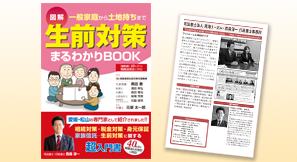
当相談室の代表 司法書士・行政書士 西森が「生前対策まるわかりBOOK」に愛媛・松山の専門家として紹介されました。