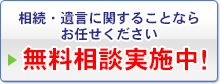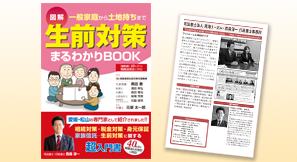2026年01月06日
Q:相続財産調査を行いたいのですが、肝心の銀行通帳が見当たらず困っているので司法書士の先生にご相談です。(松山)
はじめまして。私は松山に住む50代ですが、先日亡くなった父の件でご相談があります。父は急逝ではあったものの、松山の葬儀場で無事に葬儀も執り行い、現在は遺品整理などに取り掛かっている最中です。しかし、父がメインバンクに使用していた銀行の通帳やキャッシュカードがどうしても見当たりません。生前の父は、母に「老後の心配のないだけの貯金が銀行にある」と告げていたそうです。しかしながら、父の部屋を一生懸命探しましたが見つけられていない現状です。このまま見つからなければどうなってしまうのでしょうか。母は金銭の管理を全くやらない人なので、父がメインバンクに使用していた銀行すら知らないようで非常に困っています。これでは銀行に問い合わせも出来ないため、打開策が何かないものか司法書士の先生にご相談したくお問い合わせをいたしました。(松山)
A:法定相続人である事を証明して、可能性がある銀行に問い合わせを行いましょう。
松山相続遺言相談室までお問い合わせいただき有難うございます。
お亡くなりになったお父様(被相続人)の法定相続人である事が証明できれば、該当の銀行から残高証明を取り寄せる事が可能です。どの銀行に口座を持っているかという故人の情報を相続人が全て把握している事はむしろ少ないと思います。お父様自身が終活ノートや手帳、メモなどに銀行口座の情報をまとめているという事も可能性としては十分にあります。相続人であれば銀行に対する故人の銀行口座の有無や残高証明、取引履歴といった情報の開示請求を行う事が可能です。
しかし、ひとまず遺品整理を通じて通帳やキャッシュカードの存在を探してください。しかし、結局何も見つからなかったという場合には銀行からの郵便物や粗品などが家にないか確認し、該当しそうな銀行が見つかれば直接問い合わせを行いましょう。ここで何も手がかりが見つからなければ、仕方が無いので自宅の近くか、お父様の勤務地に近い銀行に問い合わせを行います。情報開示請求には、その口座名義人の相続人である事の証明が求められます。予め戸籍謄本の準備をしておきましょう。
相続手続きは非常に複雑で分かりにくく、なかなか手続きが進まず時間ばかり掛かり、相続人にとっては非常にストレスとなる事も多々あります。少しでもご不明点やご不安なことがございましたら、相続の専門家への問い合わせをおすすめいたします。
松山相続遺言相談室では、相続の専門家が豊富な経験をもとに松山の皆様のサポートを行っております。初回の相談は無料で承っておりますので、松山で相続のプロをお探しの皆様はぜひ松山相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。松山の皆様のご来所を松山相続遺言相談室の所員一同お待ち申し上げております。
2025年12月02日
Q:寝たきりの父がもう長くはない事を告げられました。亡くなった後は多忙だと聞いているので、相続の事について予め司法書士の先生に伺いたい。(松山)
私は松山在住の50代です。現在はほぼ寝たきりの父の介護に追われる日々ですが、もう長くはない事を医師からも言われています。死後は悲しむ間もないくらいあわただしい事を友人や知人から知っているので、今から相続の流れについて伺って、少しでも知識を付けておきたいです。父は不動産や有価証券も持っているようですが、お恥ずかしながら私の相続に関する知識は皆無です。お葬式については、同じ松山の知人から教えてもらい何とかなりそうです。相続についての流れを聞いた上で、必要と感じましたら改めて面談などでじっくりお話を伺えればと思っております。(松山)
A:相続の基本的な流れについて、ご説明いたします。
松山相続遺言相談室までお問い合わせいただきましてありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、大事なご家族がお亡くなりになってからは哀しむいとまが無いくらいに忙しいと感じる方は、数多くいらっしゃいます。事前に少しでも知識をつけておく事はとても大切です。ご逝去後の相続手続きに関する流れについて、引き続きご説明いたします。
相続手続きにおいて、お亡くなりになった方は「被相続人」と呼ばれます。そして、最初にご家族がやるべき事は遺言書の有無確認です。民法において、遺言書の内容が法定相続よりも優先される重要事項のため、遺品整理を行う際には遺言書を意識して探すように心がけて下さい。そして、遺言書が遺されている場合にはその内容に従って相続手続きを行う事になります。
続いてご説明するのは遺言書がなかった場合の基本的な流れになります。
まずは相続人の調査を行います。相続人を確定させるために被相続人の出生~死亡までの全戸籍を収集して、その際に相続人の戸籍謄本も併せて取り寄せてます。
次に行うのは、被相続人が生前に所有していた全ての財産調査です。財産が一目で分かるように相続財産目録を作成しましょう。ここで言う財産というのは、現金や貯金、不動産といったプラスになる財産だけでなく、借金や住宅ローン、その他支払いの必要な債務といった引き継ぐ相続人にとってはマイナスにはらたく財産も含まれるため、慎重な調査が必要です。相続財産目録の作成のために、銀行の通帳や不動産の登記事項証明書(不動産が有る方)、固定資産税の納税通知書、その他財産に関する全ての書類を集めましょう。
相続人と相続財産が確定したら、次に行うべきは相続方法の決定です。財産状況などにより相続放棄や限定承認を希望する場合には「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」という、決して余裕があるとは言えない申述の期限が設けられています。少しでもお早めに検討して判断するようにいたしましょう。
次に全ての相続人で遺産分割の方法を話し合う遺産分割協議を行います。その中で決まった内容は「遺産分割協議書」として書面に書き残し、そこに相続人全員で署名と捺印を行います。遺産分割協議書は相続した不動産の名義変更、銀行口座の解約を行う際に使用します。
続いて、遺産分割協議の決定に従い相続人が不動産などの名義をご自身の名前に名義変更を行う手続きを行います。
以上、基本的な流れをご説明しましたが相続手続きは複雑で難しい手続きです。想定外の事から手続きが停滞することも少なくありません。少しでもご不安やご不明点があれば相続の専門家にぜひお気軽にご相談ください。
松山相続遺言相談室では、松山の皆様から相続手続きに関するご相談を数多くいただいております。相続手続きは頻繁に行うようなことではないにも関わらずその内容は複雑で、大きなストレスに感じる方が多くいらっしゃると思います。松山相続遺言相談室では初回の無料相談を承っておりますのでぜひお気軽にご活用ください。松山で相続のプロをお探しの皆様のお気軽なお問合せを、松山相続遺言相談室の所員一同お待ちしております。
2025年11月04日
Q:母の相続において、代襲相続人がいます。司法書士の先生、この場合の法定相続分の割合について教えていただけますか。(松山)
松山の実家で暮らしていた母が、この度息を引き取りました。母は昔、祖父の相続でかなりの遺産を受け取ったと聞いていますので、今回の相続では慎重に遺産分割を行う必要があると考えています。
といいますのも、母の相続で本来相続人となるべき私の実兄はすでに他界しており、その子、私からみた甥と姪の2人が代襲相続人になるのです。したがって、今回の相続では父、私、弟、甥、姪の5人で遺産分割することになります。
私と弟は今も松山の実家近くに暮らしていますが、甥と姪は兄が亡くなったことを機に松山を離れ、今ではほとんど連絡を取り合うこともなくなってしまいました。
正直に申しますと、弟は甥と姪に財産が渡ることに対して思うところがあるようです。とはいえ、兄の大切な子どもたちですし、母の遺産を相続する権利もあります。
皆が納得する遺産分割にするためにも、法の下でそれぞれがどの程度の割合で財産を受け取ることができるのか、教えていただきたいです。(松山)
A:法定相続分の割合は、相続人の相続順位や人数の組み合わせによって変わってきます。
民法では「法定相続分」という、相続人が複数名いる場合に各人が取得する遺産の割合の目安を定めています。法定相続分は、相続人の相続順位や人数の組み合わせによって割合が変わってきますので、まずは民法の定めを確認しましょう。
(1)法定相続人と各人の相続順位
民法に定める相続する権利を有する人を「法定相続人」といい、以下のように相続順位が定められています。
- 配偶者は常に法定相続人
- 第一順位 子や孫などの直系卑属
- 第二順位 父母や祖父母などの直系尊属
- 第三順位 兄弟姉妹などの傍系血族
配偶者は常に法定相続人となりますが、その他の親族は相続順位に沿って相続権が与えられます。第一順位の人が存在すれば、第二順位以下の人が法定相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどいない場合に、すぐ下の順位の人が法定相続人となります。
松山のご相談者様のケースでは、お父様は配偶者として法定相続人であり、松山のご相談者様、弟様、甥御様、姪御様の4人は共に第一順位の法定相続人です。
(2)法定相続分の割合
法定相続分の割合は、民法で以下のように示されています(以下、民法第900条より抜粋)。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上を踏まえますと、まず、配偶者であるお父様と、その他の相続人とで1/2ずつに分けられます。次に、配偶者以外の相続人が、1/2の割合をそれぞれ等しく分け合うことになりますが、このとき、本来の相続人である亡くなったお兄様を1人分として考えます。したがって、1/2の割合を、松山のご相談者様、弟様、亡くなったお兄様の3人で割り、1人あたりの法定相続分は1/6となります。
最後に、亡くなったお兄様の法定相続分(1/6)を、代襲相続人である甥御様と姪御様の2人で割るので、1人あたり1/12となります。
- お父様:1/2
- ご相談者様:1/6
- 弟様:1/6
- 甥御様:1/12
- 姪御様:1/12
法定相続分の割合は以上となりますが、遺産分割協議によって全員の納得する遺産分割ができれば、この法定相続分に従う必要はありません。
松山のご相談者様のように代襲相続が発生するケースの他にも、さまざまな理由で相続関係が複雑になることもあります。松山にお住まいで遺産分割についてお悩みのある方は、どうぞお気軽に松山相続遺言相談室までお問い合わせください。初回完全無料にて、相続の専門家が丁寧に対応させていただきます。
2025年10月02日
Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になるのか司法書士の先生にお伺いしたいです。
先日、松山に住む実母から再婚相手が亡くなったと連絡が入りました。私の父と母は私が成人したタイミングで離婚しました。その後、母は別の方と再婚して松山で暮らしていました。私は再婚相手の方と面識はありませんでしたが、母のことが心配になり、葬儀に参列することにしました。その際、母から相続手続きを私の方で引き受けてくれないかと言われました。母によると、今回の相続で私も相続人になるそうです。面識のない方の相続手続きを引き受けるのは、正直荷が重いです。私は実母の再婚相手の相続人なのでしょうか。万が一相続人だった場合、相続を断ることはできますか?(松山)
A:実母の再婚相手と養子縁組をしていないのであれば、相続人ではありません。
今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の相続人ではありません。
法定相続人である第一順位の子(直系卑属)は、実子か養子に限ります。したがって、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組をしていなければ、相続人ではありません。ご相談者様のご両親が離婚されたのはご相談者様が成人したタイミングとのことですので、再婚相手の方と養子縁組をしていたとしたら成人後の事になります。成人が養子縁組をする場合、養親または養子が養子縁組届を提出しますが、届出には両方が自署押印を行う必要があります。そのため、再婚相手の方の養子になっていたとしたら、ご相談者様ご自身が書類に自署と押印をしているため把握されているかと思います。この手続きを行っていなければ養子ではありませんので、再婚相手の方の相続人ではありません。
万が一、養子縁組をしていた場合には今回相続人になります。ご相談者様が相続人だった場合、相続をしたくないというご意向でしたので、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。なお、相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますのでご注意ください。
今回のご相談内容については以上となりますが、相続ではご自身での判断が難しい手続きでお困りの方が多くいらっしゃいます。松山で相続手続きに関するご相談なら、松山相続遺言相談室にお問い合わせください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。松山相続遺言相談室の相続手続きの専門家が松山の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。
2025年09月02日
Q.司法書士の先生にお伺いします。父名義の不動産について、相続登記がまだ終わっていません。このままにしておいても差し支えないのでしょうか。(松山)
私は松山に暮らす50代の女性です。父の不動産について気になることがあり、ご相談させていただきます。
父は3年前に亡くなり、相続人である私と妹、弟の3人で遺産分割協議を行い、無事に話し合いはまとまりました。ところがその後、父の名義で残されていた不動産が別にあることがわかりました。
その土地についても新たに協議を進めようとしましたが、弟が海外在住でなかなか連絡が取れず、気づけば時間だけが過ぎてしまいました。加えて、その土地は私たちにとって特別に価値が高いものではなかったため、「急がなくてもよいのでは」という気持ちも正直ありました。
そんな折、ニュースで「相続登記が義務化される」という内容を目にし、放置している土地のことが心配になってきました。処罰の対象になるのは避けたいのですが、協議が停滞しているのも事実です。父が亡くなったのは3年前であり、義務化の施行がされたのは2024年からと聞いておりますので、今回のケースが対象になるのかどうか判断に迷っています。
不安を残したままにしておくのも落ち着かないため、2024年から始まった相続登記の義務化について、具体的に教えていただけないでしょうか。(松山)
A.相続登記の申請義務は2024年4月1日から施行されますが、それ以前に発生した相続であっても義務の対象になりますので注意が必要です。
松山相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。今回ご質問いただいた「相続登記の義務化」について回答いたします。
「相続登記の義務化」が施行された背景としては、これまで不動産を相続した際に行う名義変更手続き(相続登記)には期限が定められておらず、被相続人の名義のまま放置されるケースが数多くありました。
その結果、所有者不明の土地や建物が増え、公共事業や都市計画の妨げになったり、老朽化による倒壊で周辺住民へ危険を及ぼすなど、さまざまな社会問題を引き起こしていました。
こうした現状を踏まえ、相続登記を適切に行うことを目的として、申請義務化が導入されることになったのです。
改正法によれば、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、違反すると10万円以下の過料に処される可能性があります。ここでいう「所有権を取得した」とは、相続開始時点を指します。
なお、この義務は2024年4月1日以降に始まった相続だけでなく、それ以前に発生していた相続についても適用されます。ただし「所有権を取得したことを知った日」または「施行日」のいずれか遅い日から3年間の猶予が与えられるため、すでに相続登記をしていない方も、今のうちに早めの対応を進めておくことが安心につながります。松山にお住まいの方に向けて、当事務所では初回無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
さらに、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらず登記が進められない場合には、法務局にて「相続人申告登記」を行うことが可能です。これを申請しておけば、期限内に本来の相続登記ができなくても所有者不明土地と扱われず、過料の対象からも除外されます。
松山相続遺言相談室では、松山を中心に相続に関する数多くのご相談を承っております。地域事情に詳しい司法書士が、ご依頼者一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートいたします。
相続登記でお悩みの方は、ぜひ松山相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。松山にお住まいの皆様、また松山周辺で信頼できる専門家をお探しの方からのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。